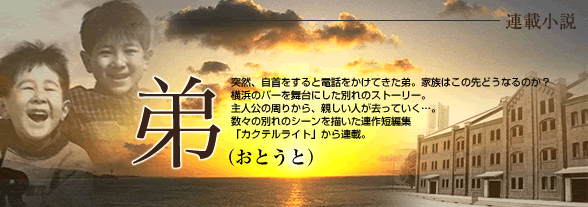「兄さんには、売上の中の俺の取り分を幸子に渡してほしいんだ。
毎月、チーフから受け取って、それを幸子の口座に振り込んでほしい」
和幸は、空になったアイスペールを持ってカウンターの中に入りながら言った。
「どうして俺なんだ?そういうことならチーフに頼めばいいじゃないか」
川口は相馬を見たが、相馬は目を合わせなかった。
「もちろん、兄弟だからって只でやってとは言わないよ」
そういって、レジの下の引き出しから封筒を出してテーブルまで戻り、川口の前に置いた。
「100万入ってる。兄さん独立するんでしょ?金必要なんでしょ?」
例えサラリーマンの時と同じ仕事をするといっても、独立する人間には信用がない。
それまでの自分の扱ってきた金額の大きさが自分自身の価値と錯覚していた。
銀行はそんなに甘くない。
貯金もさほどなく、資金調達に行き詰まっていた。
まして家の貯金で独立するわけにはいかない。
最近、妻の一美とうまくいっていない。年々かさむ教育費などで口論が絶えない。
一美は、給料の金額を実際にもらう金額を少なく言っていると思っている。
川口が銀行からおろし、毎月の必要な額を差し引いて明細書と一緒に一美に渡している。
その明細書すら偽造していると思っている。
その詐取した金は、女につぎ込んでいるのは?と疑っていた。
真由美は、会社の外に借りている仕事場にも出入りしているが、
一美は、20才も違うこの真由美とできているんじゃないか?と疑っている。
詰め寄られたこともあった。
アシスタントだから普通のことと思っていたが、一美はそう考えてはいなかった。
だから、独立したいから家の貯金を崩してくれとは言えなかった。
「どうして知ってるんだ?」
「母さんに金の無心したでしょ?
俺もこの店を出すときに少し出してもらったから偉そうなことは言えないけど、
親父が死んでもう収入がないんだよ?母さんは。年金と貯金で暮らしてるようなもんでしょ?
そういう人から借りるのはどうかと思うよ」
「母さんが言ってたのか?」
「ああ、もしかしたら老人ホームに入るかもしれないからって
手を着けなかった貯金をおろそうかと思うんだけどけど、
どう思う?って電話がかかってきたよ。」
この時、川口は、和幸が「真由美がいていいのか?」と言った理由が分かった。
もちろん自分自身が、犯罪に手を出したことを知られるということも躊躇したのかもしれないが、
この話もあっての忠告だったのかもしれない。
ただ、もう一緒に独立することはなくなったのだから、どうでも良かった。
むしろ自分の出来の悪さをさらけ出すことで、
それを知った真由美とは一緒に仕事ができないんだと自分に言い聞かせたいという気持ちもあった。
「あんまり母さんに心配かけるなよ。
母さんは、兄さんが本当は会社をリストラされるんじゃないのかって悩んでる。
だから、会社を作る資金は援助しなけれなならないって思ってるよ。」
母親から資金を出してもいい、という連絡が来たのは先週だった。
川口は、申し訳ないという気持ちと良かったという安堵の気持ちの両方を感じながら
その返事を聞いた。
「いい年して、スネをかじるのはもうやめなよ。母さんを困らせるなよ」
諭すような和幸の言葉に川口は激情を抑えられなかった。
和幸の胸ぐらを掴むのと同時に和幸の顔面を殴打した。
座っていた椅子ごともんどり打って後ろに倒れた。
真由美がハッとした顔をしたが、何も言わなかった。
「おまえに言われたくねえよ!金を借りたって捕まらないんだぜ?
ムショにぶち込まれるおまえが偉そうにいってんじゃねえよ」
和幸は、ゆっくりと起きあがり、椅子を直しながら言った。
「そうだね。俺の方がもっと悪いね。
でも、こんな俺だからせめて兄さんだけでもちゃんとしないと母さんが可哀想だよ」
川口は、和幸の母親が可哀想という言葉で我に返った。
「殴って悪かった」
「理由はともかく俺はもういなくなるんだ。母さんを守れるのは兄さんだけなんだよ?」
「わかった。この金は預かっとく」
そうは言ったものの、100万では足りなかったが、
足りない分は母親から借りるとは言えなかった。
「毎月、店の上がりから幸子さんに振り込めばいいんだな?」
「ああ、チーフから預かってほしい。詳しいことは後からチーフに聞いてよ」
「おまえ、さっきもういなくなるなんていってたけど、
何か良くないこと考えてるんじゃないだろうな?
帰ってきたら、またここで仕事するんだろ?場合によっちゃ幸子さんも呼び戻して」
この台詞は、ドアの向こうで来ている幸子のために言った台詞だった。
「いや、もう幸子とはきっぱり縁を切って、
俺っていう存在を娘の真沙美の心の中に残さないようしたいんだ。人殺しの娘にしたくないんだ」
「でもどれくらい入るかわかんないけど刑期を済ませれば普通の人じゃないか」
「なに言ってんの?前科者だよ?俺。
前科っていうのはさ、白いシャツについた血のシミみたいなもんなんだよ。
何度も洗濯して漂白剤かければ見た目は真っ白になる。
刑務所に入るってことは、この洗濯や漂白剤をかけるのと一緒。
見た目をきれいにするためなんだ。
でもね、ルミノール反応を見れば血が付いていたなんて一発でわかっちゃうんだよ。
犯罪者っていうシミはどんなことをしたって消えないんだ」
「でも、幸子さんはそんなおまえでもいいって言うかも知れないだろ」
「幸子は言うかも知れない。
でも、何も知らない真沙美が、
もし何年かして誰かに君の父親は人殺しだよ、って言われたらって思うとたまらないんだ。
俺だって帰ってきたら迎えにいきたいって気持ちはあったよ。
こんなに大きくなったんだって抱きしめたいよ。
でも犯罪者にはその資格はないんだ。だから俺も堪えるしかないんだ。
幸子がなんと言おうと俺は縁を切る」
それまで静かに話していた和幸が、初めて強い口調で少し涙声になって言ったのを見て、
決心の堅さを感じた。幸子はどう思っただろうか?川口の頭の中をよぎった。
「炭酸もなくなっちゃったね」
そういって和幸がカウンターに入った時、店のドアが開いた。
きつい目の感じと堅そうな身なりの男が、少し笑顔を見せて立っていた。
一目で警察の人間と思った。
「ああ沢木さん。適当な所に座ってください」
「そろそろかなと思ってきたんだけど、早かったかな?」
「大丈夫ですよ。もう少しで終わりますから」
「兄貴の正幸です。兄さん、この人がつり仲間で横浜署の刑事の沢木さん」
川口、真由美、チーフの相馬、沢木、ドアの向こうの幸子、そして和幸。
この異様な会合も、警察の人間が加わったことで、確実に終わりが近づいていた。
(つづく) |