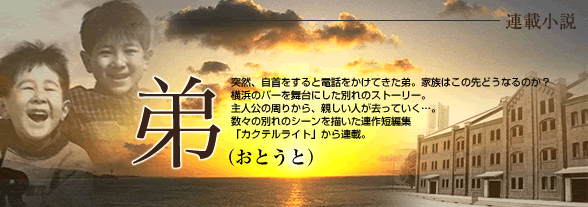真由美は、川口と和幸のただならぬ雰囲気に凍り付いたように入り口の外にたっていた。
外の雨が、まだ強く降っているのがジーンズがすねの辺りまで濡れているのでわかる。
川口は、一瞬睨み付けるように真由美を見た。
知られたくないという気持ちが態度に現れていた。
和幸が立ち上がり入り口までいき、ドアをいっぱいにあけて中に誘なった。
「どうぞ。まだ。雨強いようですね」
普通の客への世間話のように和幸が言うと、真由美はぎこちない笑みを浮かべて
「ありがとうございます」とだけ答えた。
川口は、さっきの話の続きを再開したいという気持ちと
真由美に聞かれたくないという気持ちの両方が交錯し、少し動揺していた。
そして、徐に立ち上がると真由美に近寄った。
真由美は、和幸を見る顔とは明らかに違う強い視線で川口を見た。
「少しいいか」
川口は和幸に言うと、店の奥に真由美を連れていった。
「私、来てはいけなかったんじゃないですか?」
「うん。正直言えばできればきてほしくなかった。
でも、明日の企画書を渡さなかったのは俺のミスだし、
君の企画書のチェックも必要なんだろ?今、ここで話していることは俺のプライベートだ。
だから仕事の方を優先するのは当然だ。」
「でも…」そう言いかけた真由美を制して、川口は続けた。
「こんな時に、こんな所でいうべきことじゃないのは分かってる。でも、今しかないんだ」
意を決したような川口の強い口調にも表情を変えなかったが、
明らかに店にきた時よりも緊張しているのは、
持っている手提げ袋が僅かに震えているので分かった。
「俺の新しい事務所に来ること、考えてもらえたかな?」
真由美にとっては場違いな問いかけに感じたのだろう。
表情のないクールな顔に、少し怒りのような表情が入り交じった。
「どうして、今なんですか?」
「説明はしにくい。でも、今でなければならない理由があるんだ。
そして、もし来てもらえるなら、ここに残ってこれから始まることを一部始終、
俺と見届けてもらう。
そして、もし断るつもりなら、君の企画書を置いて店を出ていってほしい。
俺が打ち直して、朝、会社の君のパソコンに送る」
仕事のために、わざわざ目黒の自宅から横浜まで来た人間に、
自分と心中しないなら帰れと言っているようなものだった。
いくら親しくても、酷い言い方なのは十分承知していた。
相変わらず川口から視線を外さない真由美。気の強さを表している。
普段の穏やかで冗談が得意で、子供のような笑顔見せる真由美はそこにはいなかった。
大きな決断を迫られている状況が真由美から普段の柔らかな表情を消していた。
沈黙が続いた。誰も話さない。
離れたテーブルで、和幸が口に運ぶグラスの中の氷の音と、
ドナサマーのバラードだけが唯一の音だった。
真由美の、先ほどの強い視線の表情が困惑の表情に変わり、そして視線が下に落ちた。
川口は、真由美は必ず一緒に来ると信じていた。
待遇に大きな差があっても、絶対に俺と仕事をしたいと思うはずだ。
彼女は仕事をモチベーションで選ぶ。だから余計に俺と一緒に…。
真由美は静かに顔を上げると少しだけ微笑むような顔で言った。
「お断りしたいと思います」
「え?」
予想外の答えに川口は狼狽した。
今日、これから起こることを真由美に見せ、
そして一緒にこれからの対策を考えたいと思っていた。
というよりも、そのことだけを考えていた。真由美は来てくれるものとして…。
「どうして?」会社の規模や条件など何一つ、今の会社に勝るものはない。
すべてが劣っているといってもいい。
唯一、自分という人間がいることだけが、新しい事務所が今の会社に勝てるファクターだ。
川口はそう信じていた。
そして、だからこそモチベーションで仕事をする彼女が、
ただ待遇がいいだけの今の会社に残ると答えるとは思わなかった。
衝撃だった。
ある意味では、和幸の人を殺したという告白以上に心に突き刺さった。
そしてえも言われぬ孤独感を感じた。
真由美と川口の会話の内容を知ってか知らずか、和幸は煙草に火をつけて、
まるでなにも聞こえないような無関心さを装っていた。
「でも…」真由美が話し始めた時、放心状態に近かった川口は一瞬気づかなかった。
「会社も辞めます。もうあの会社にいる理由がないですから」
「俺が辞めるから?」
「ええ」
「だったら、一緒に…」それ以上は続けなかった。
女性が決意した後に見せる悟りきったような笑顔は、もう覆すのは難しいと思った。
「帰ります。企画書、よろしくお願いします」
大袈裟に頭を下げた真由美を見て、川口は言った。
「いてくれないか、ここに。君が会社に残らないならいてもらったほうがいい。」
気落ちしたように弱々しくいった川口に真由美は
「いいんですか?」
「ああ」
真由美は何か胸につかえていたものが落ちたような一種晴れやかな顔をしていた。
この顔だ、普段の真由美は。
川口がそう思った瞬間、チーフの相馬が目配せをして店の外に出ていった。
幸子が来たのだ。
出ていく相馬に何を問いかけでもなく、
和幸は残り少なくなったグラスの底を静かに見つめていた。
(つづく)
|